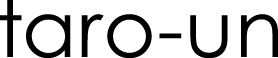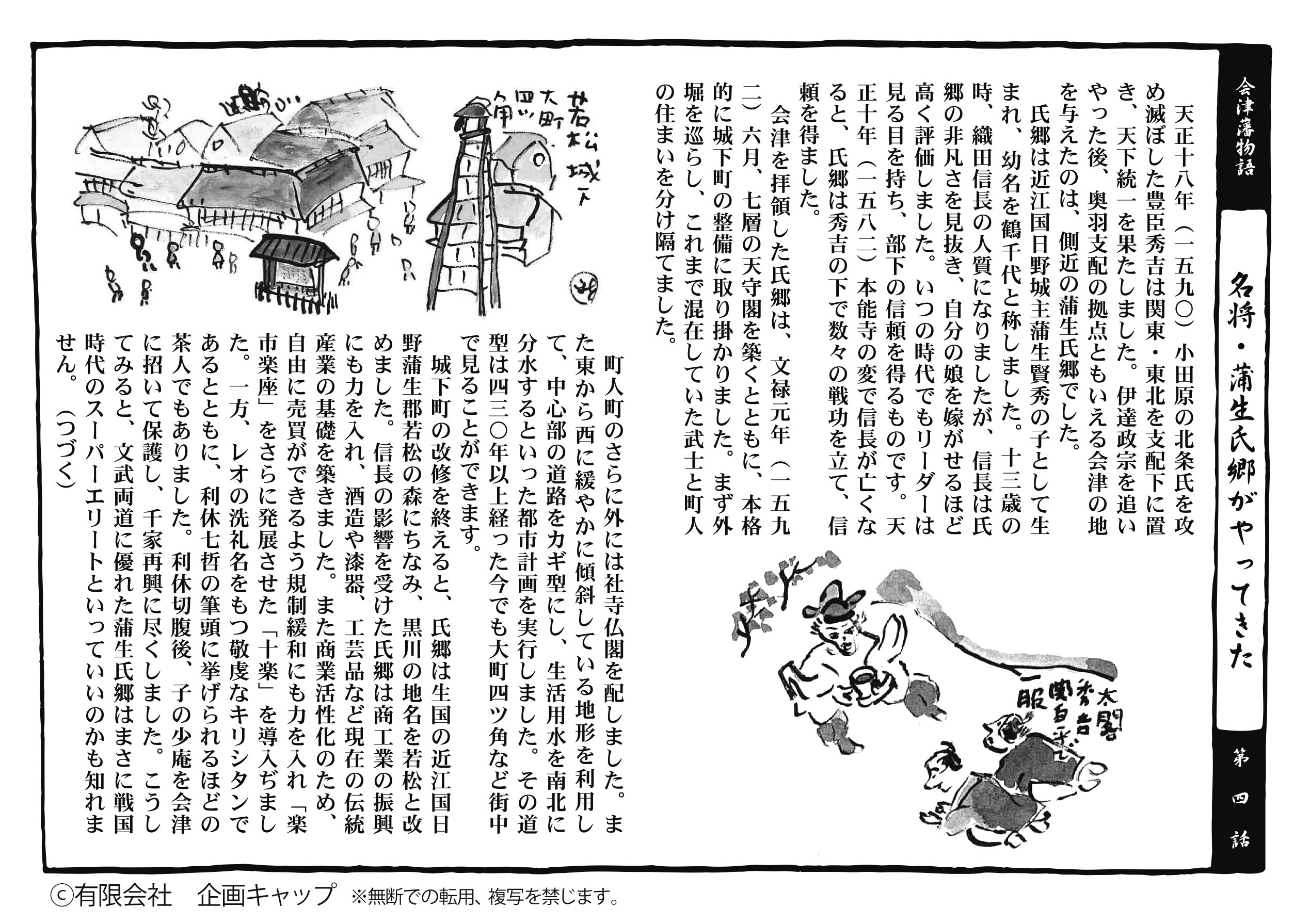会津藩物語
天正十八年(一五九〇)小田原の北条氏を攻め滅ほした豊臣秀吉は関東·東北を支配下に置き、天下統一を果たしました。伊達政宗を追いやった後、奥羽支配の拠点ともいえる会津の地を与えたのは、側近の蒲生氏郷でした。
氏郷は近江国日野城主蒲生賢秀の子として生まれ、幼名を鶴千代と称しました。十三歳の時、織田信長の人質になりましたが、信長は氏郷の非凡さを見抜き、自分の娘を嫁がせるほど高く評価しました。いつの時代でもリーダーは見る目を持ち、部下の信頼を得るものです。天正十年(一五八二)本能寺の変で信長が亡くなると、氏郷は秀吉の下で数々の戦功を立て、信頼を得ました。
会津を拝領した氏郷は、文禄元年(一五九二)六月、七層の天守閣を築くとともに、本格的に城下町の整備に取り掛かりました。まず外堀を巡らし、これまで混在していた武士と町人の住まいを分け隔てました。
町人町のさらに外には社寺仏閣を配しました。また東から西に緩やかに傾斜している地形を利用して、中心部の道路をカギ型にし、生活用水を南北に分水するといった都市計画を実行しました。その道型は四三〇年以上経った今でも大町四ツ角など街中で見ることができます。
城下町の改修を終えると、氏郷は生国の近江国日野蒲生郡若松の森にちなみ、黒川の地名を若松と改めました。信長の影響を受けた氏郷は商工業の振興にも力を入れ、酒造や漆器、工芸品など現在の伝統産業の基礎を築きました。また商業活性化のため、自由に売買ができるよう規制緩和にも力を入れ「楽市楽座」をさらに発展させた「十楽」を導入ちました。一方、レオの洗礼名をもつ敬虔なキリシタンであるとともに、利休七哲の筆頭に挙げられるほどの茶人でもありました。利休切腹後、子の少庵を会津に招いて保護し、千家再興に尽くしました。こうしてみると、文武両道に優れた蒲生氏郷はまさに戦国時代のスーパーエリートといっていいのかも知れません。 (第五話へ つづく)
| 歴史銘菓『 会津藩物語 』 | ||||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 |
| 第6話 | 第7話 | 第8話 | 第9話 | 第10話 |