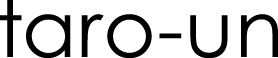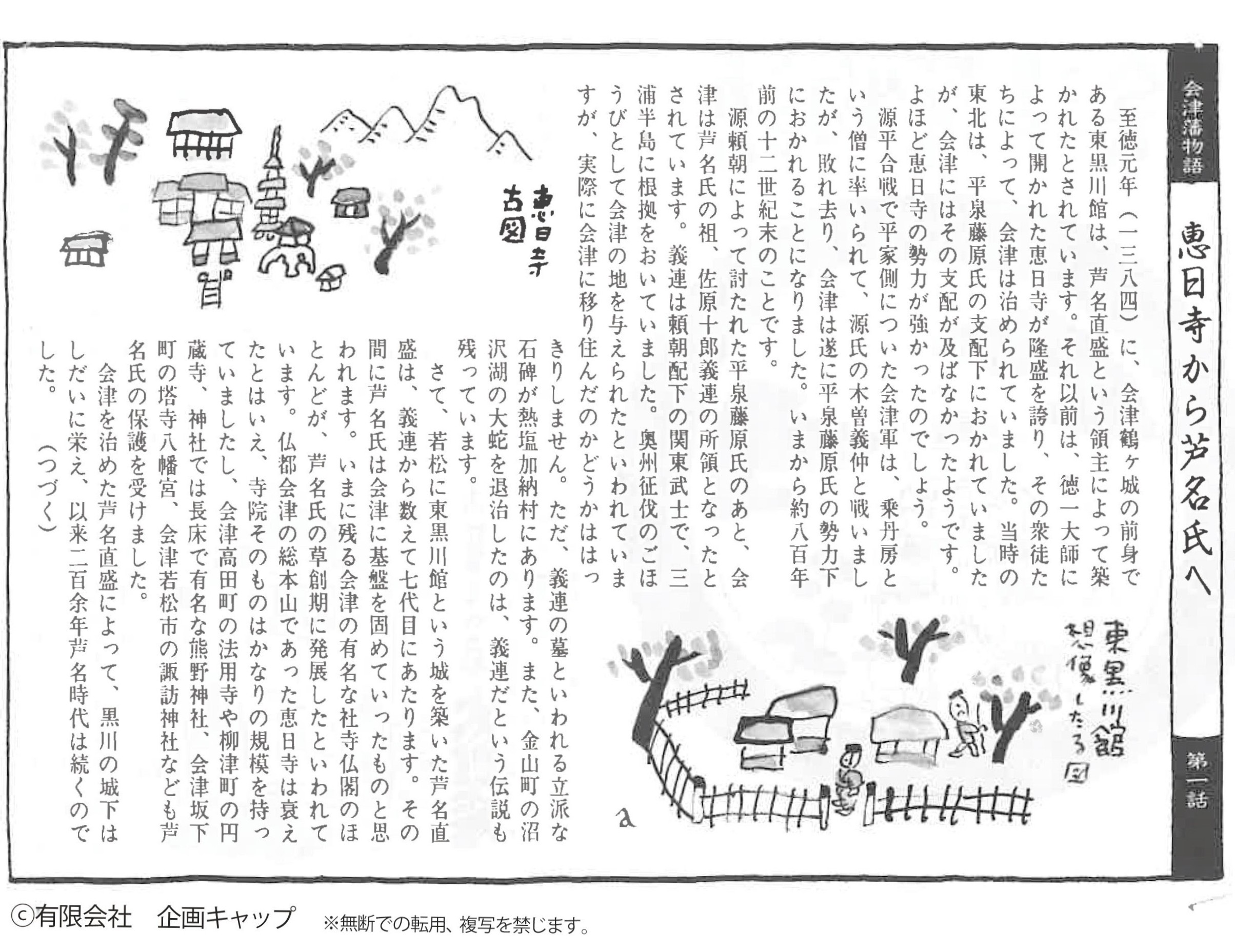会津藩物語
至徳元年(一三八四)に、会津鶴ヶ城の前身である東黒川館は、芦名直盛という領主によって築かれたとされています。それ以前は、徳一大師によって開かれた恵日寺が隆盛を誇り、その衆徒たちによって、会津は治められていました。当時の東北は、平泉藤原氏の支配下におかれていましたが、会津にはその支配が及ばなかったようです。よほど恵日寺の勢力が強かったのでしょう。源平合戦で平家側についた会津軍は、乗丹房という僧に率いられて、源氏の木曽義仲と戦いましたが、敗れ去り、会津は遂に平泉藤原氏の勢力下におかれることになりました。いまから約八百年前の十二世紀末のことです。
源頼朝によって討たれた平泉藤原氏のあと、会津は芦名氏の祖、佐原十郎義連の所領となったとされています。義連は頼朝配下の関東武士で、三浦半島に根拠をおいていました。奥州征伐のごほうびとして会津の地を与えられたといわれていますが、実際に会津に移り住んだのかどうかははっきりしません。ただ、義連の墓といわれる立派な石碑が熱塩加納村にあります。また、金山町の沼沢湖の大蛇を退治したのは、義連だという伝説も残っています。
さて、若松に東黒川館という城を築いた芦名直盛は、義連から数えて七代目にあたります。その間に芦名氏は会津に基盤を固めていったものと思われます。いまに残る会津の有名な社寺仏閣のほとんどが、芦名氏の草創期に発展したといわれています。仏都会津の総本山であった恵日寺は衰えたとはいえ、寺院そのものはかなりの規模を持っていましたし、会津高田町の法用寺や柳津町の円蔵寺、神社では長床で有名な熊野神社、会津坂下町の塔寺八幡宮、会津若松市の諏訪神社なども芦名氏の保護を受けました。
会津を治めた芦名直盛によって、黒川の城下はしだいに栄え、以来二百余年芦名時代は続くのでした。 (第二話へ つづく)
| 歴史銘菓『 会津藩物語 』 | ||||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 |
| 第6話 | 第7話 | 第8話 | 第9話 | 第10話 |